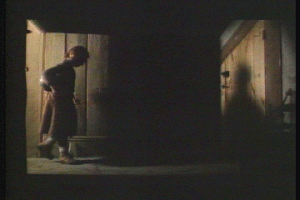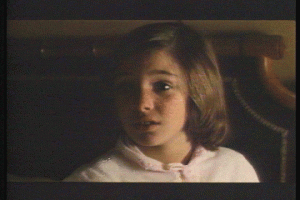父を偶像視する少女。それは何も偏執的なものじゃなくって、誰でもがかつて抱いていたであろう想像的な世界。少女は、父の出身地である「南」、父が決して帰ろうともせず音信さえ途絶えている「南」に想像を膨らませるのです。「エル・スール」とは「南」ということですね。でもあるとき、父には密かに思いを抱いている忘れ難い過去の女があることを知るのです。父と娘だけで閉じていた幸せな想像的関係が、次第に変質していきます。完璧で偉大であった父が、一人の悩める男として少女の目の前にふいに現れてきます。そんな矢先に父は自殺してしまうのですね。少女は想像の世界であった「南」へと旅立ちます。それは少女から娘へという旅でもあるだろうと、そんな予感を漂わせて映画は終わります。ここで、想像することは観客へと受け継がれるのです。
この監督は、本当に映画を丹念に丹念につくりあげます。その濃密さは写真をみただけでもわかると思います。どのシーンをとっても「まるで絵画のように」という陳腐ないいまわしでさえも納得できてしまうほどに計算された深い陰影に満ちています。
その丹念さは、演出にも現れます。たとえばお父さんの自殺のシーン。上の写真の風景を右側からパンして入ってくるんですけど、はじめは写真の中の左側の赤くぼんやり光ってる夕日は映ってません。徐々にカメラが動いて、光が映り込んだ時、その下にお父さんが横たわっていることを観る人は知るのですね。


それとか上のきれ~いな並木道が家の前を走っているのですが、左がほんとに幼い子供時代(下の左)で、そこをず~っと向こうに向かって自転車で走っていくんですね。帰ってきたとき(右の写真)は少し大人びてる(下の右の写真)わけで、これは時間が経過しましたよっていうよくある演出なんですけど、あの白のラインがぱっと映ったときには、同じ道ががらっと変わったっていう印象を受けるんですね。しかもこの道は、お父さんがバイクで仕事場から帰ってくる道で、少女がいっつも心待ちに待っていた道なんですね。お父さんの、南に住んでるお母さんがやってくるのもこの道の先から。だから、この道の印象が変わるってことはとても重要な意味をもってるんです。
想像というものが、どれだけ豊かで触覚的ともいえるような生々しい世界をつむぎだすかということをこの映画はまざまざと見せてくれます。近寄り難い父に対して抱く想像。「南」という未知の世界に対して膨らませる想像。知り得ないということは、それだけで価値あることなのではないかと考えてしまいます。今は、知り得ない世界がどんどんなくなっているような気がしますね。そんな気がするだけで、実際は知り得ないことだらけなのでしょうけど。
イームズの「パワーズ・オブ・テン」という映像作品がありますよね。二人のカップルを上から写した映像から始まって、どんどんどんどんカメラは上に上がっていって、大気圏を通り越して、太陽系を通り越して、銀河系を通り越して、宇宙の果てまでいっちゃう。そこからまたカメラは引き返して、今度は人体の細胞の中にまで入っていって、DNAの中に入っていって、原子の世界まで行っちゃって、最後は電子の世界までいっちゃう。これはどの単位の世界にも、似たような世界が開けるってことを示しているともいえるし、「フロンティア」というものが、それまでは宇宙に対して、人がいける可能性があるところを意味していたのが、人体の中にまでフロンティアが進んだということを明確に示しているわけです。
「エル・スール」のような豊かな触覚的な「現実的な」想像を膨らませることが、この先、人にはできなくなっちゃうんでしょうか。インターネットが普及することで、皆が全てを知り得るという錯覚が生まれているように思います。そんな錯覚が奪ってしまう豊かさを、この映画は感じさせてくれるのでしょう。